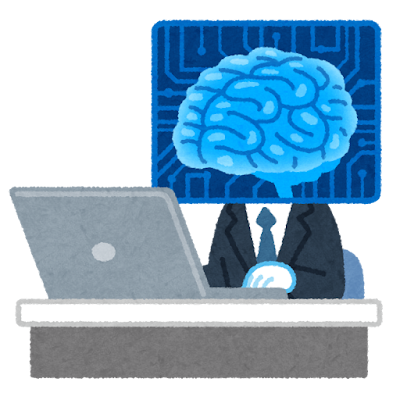従来のSIビジネスは、顧客の事業目的を達成するためのITシステム構築を請け負うことが中心でした。しかし、生成AIの登場により、この前提が根底から覆されようとしています。
AI駆動開発の普及と内製化のの拡大
GitHub Copilot Workspaceのような生成AIを使ったシステム開発開発(AI駆動開発)ツールは、「何をしたいか」を入力するだけで仕様作成からコーディング、テストまで自動化し、人間の役割を最小限に抑えます。この流れは、日米のIT業界における構造的な違いと密接に関係しています。
米国では、シリコンバレーが象徴するように、起業と転職が活発で、雇用の流動性が高いことが特徴です。企業は、プロジェクトや開発フェーズに合わせて、必要なスキルを持つITエンジニアを迅速に採用し、プロジェクト終了後には解雇することが一般的です。このような柔軟な雇用環境があることで、ITエンジニアの7割がユーザー企業に所属するという内製化志向を促進してきました。
ユーザー企業は、開発コストを直接負担するため、開発生産性向上によるコスト削減に強い関心を持ちます。そのため、クラウドコンピューティング、アジャイル開発、DevOpsといった生産性向上のための技術や手法を積極的に導入し、近年ではAI駆動開発もその流れに組み込まれています。
一方、日本では、 終身雇用を前提とした雇用慣行が根強く、一度採用した社員を解雇することは容易ではありません。このため、企業はITエンジニアを直接雇用することに慎重になります。
なぜ慎重になるかと言えば、要件定義や概要設計は少ない人手でいいのですが、詳細設計やコード生成、テストでは大量の人手を投入し、運用や保守では、再び少ない人手となります。この大量の人手に合わせて社員を雇ってしまうと、日本の雇用環境では解雇できないので、大きなシステム開発プロジェクトがないときは、余剰人員となってしまいます。
このようなことにならないように、人員の需要がピーク時の要員を外注に任せてしまおうとなったわけです。これにより、 ITエンジニアの7割がITベンダー/SIerに所属するという構造が定着しました。
このような前提があればこそ、SIerは、顧客へのエンジニア派遣や受託請負の工数を収益源とするビジネスモデルが確立できました。そのため、開発生産性向上は、自らの収益を減少させる要因となり、積極的に取り組むインセンティブが働きにくい状況でした。
しかし、近年、DXの波が押し寄せ、企業は競争力強化のために先進技術を活用する必要性に迫られています。SIerに依存した従来の開発体制では、スピード感や柔軟性に欠け、最新技術への対応も遅れがちです。そのため、ユーザー企業は、内製化に舵を切り始め、ITエンジニアの採用や育成に力を入れるようになっています。
AI駆動開発によるSIerの変化
AI駆動開発ツールは、ユーザー企業の内製化を加速させることになります。業務に精通したユーザー企業の担当者が「何をしたいか」を入力することで、SIerに頼ることなくシステム開発が可能になるからです。もちろん、エンジニアが直ちに不要にはなりませんが、その役割は変わり、必要人数も減少するでしょう。
SIビジネスは、今後どうのようになるのでしょうか? 要点は、以下の2つです。
- エンジニアの仕事はなくならないが、仕事をこなす上でのタスクの構成が大きく変わる。
- 「人月ビジネス」はなくならないが、単金は大幅に下がり、実質的に崩壊する。
この2つについて、さらに掘り下げてみます。
エンジニアの仕事はなくならないが、仕事をこなす上でのタスクの構成が大きく変わる。
「コードを書く」タスクは、ほぼAIに置き換えられるでしょう。どのような機能を実装したいのかを定義すれば、コードの生成は、AIに任せられます。さらには、その上位のプロセスである、何のためにどのようなシステムを開発すべきか、それがビジネスにどのような影響を与えるのか、そのためには、どのようなインフラやプラットフォームを選定すべきか、既存システムとの連携や統合をどのように進めればいいのかと言ったより上流工程のタスクの需要が増加します。
今でも、大手の元請企業はこのようなことを行い、コード生成を下請けに任せていますが、まさにこのような「下請けの仕事」は、短期間のうちに消滅する可能性があります。
また、今元請が行っているタスクも、相当部分がクラウド・サービスやAIに置き換わり、仕事量は減少します。また、ユーザー企業が自分たちでやってしまいます。そうなるとさらに上流のデジタル技術を前提とした「新しいビジネス・モデルの提案」や「ビジネス・プロセスの変革」、「新しいビジネスを安定稼働させるためのシステムアーキテクチャのあるべき姿」といった、業務や経営に立ち入った議論ができるようにならなくてはなりません。
つまり、システム開発全般についての包括的知識、それを活かしたビジネス提案といった領域へと知識やスキルをシフトしていく必要があります。コード生成しかできない、ましてや、「Javaは分かるけどPythonは無理」では仕事になりません。
この一連のトレンドは、先にも書いたとおり、内製化の流れを加速します。そうなると、アジャイル開発、DevOps、クラウドを前提とした内製チームとともに、ビジネスを生みだす共創領域に対応できなくてはなりません。技術的な知識やスキルだけではなく、コミュニケーションやファシリテーション、アイデア創出と言ったスキルも重要となります。
このような状況を想定すると、これまでにも増して、「基礎的な知識やスキル」が、重要性を持ちます。それは、ソフトウェア工学です。ソフトウェア工学とは、ソフトウェアの開発・運用・保守に関して体系的・定量的にその応用を考察する学問分野です。
システム開発は、ソフトウェア工学に基礎に置き、AIツールは、この考え方を効率よく、かつ高品質に実践する手段です。どのように使いこなせば、システムの機能や性能、品質や生産性を向上できるかは、この基礎の上になり立っています。また、アジャイル開発やDevOpsも、ソフトウェア工学の基礎に基づくものであり、体系的・定量的な改善を進めるにも極めて重要です。
「要件を与えれば、コードを出力する」タスクは、もはや人間の仕事ではなくなります。より包括的にシステムの開発や運用といった全体を捉えられる能力が、求められるようになります。さらには、ITを前提としたビジネスを考える力も必要とされ、人間が果たす役割は、よりレベルの高い戦略的な思考や創造的な問題解決に注力することになります。
「人月ビジネス」はなくならないが、単金は大幅に下がり、実質的に崩壊する。
上記のような移行が進んだとしても「人間がコードを書く」という仕事を続けるとしたら、「AIがコードを書く」場合よりも、コストパフォーマンスに秀でる必要があります。仮にAIによって生産性が、50%向上すると仮定すれば、単純に計算して単金は半額以下でなければ、AIを使いこなしてコードを書いているエンジニアとは対等ではありません。今は、できるエンジニアと未熟なエンジニアでは、同じ機能を実装するにも生産性は何倍も違います。「未熟なエンジニア」がAIを使えば、生産性という観点だけ見れば、遜色がなくなる可能性はあります。そうなると、「ベテランだから単金は高く、若手は安い」という常識も成立しなくなります。
もちろん、エンジニアの能力は、コード生成の生産性だけはありませんから、このような単純な比較は成り立ちません。ただ、上位のタスクへ移行しなければ、このような知的力仕事の単金には、常に下げの圧力がかかり続けますから、利益は厳しいものとなります。
また、上位にシフトすることは、「工数への対価」ではなく、「価値への対価」に変わることになります。これまで同様の「単金:〇〇万円×労働時間」という単純な図式は成立せず、これまで同様の収益のあげ方はできなくなるでしょう。
これを、分かりやすく説明するなら、「その作業量なら〇〇人月で引き受けさせていただきます。これが私どもの精一杯の金額です。いかがでしょうか?」というやりとりから、「その仕事の内容であれば、〇〇万円かかります。この金額でよろしければ、お引き受け致しますが、どうされますか?」ということになるでしょう。
AIは、これまで専門家でなければできなかったことを代替し、ユーザー企業は、ITサービスを自ら構築・運用できるようになります。SIerは、従来の「ITシステムを作る」という存在意義を失い、新たな役割を模索する必要に迫られています。
実践で使えるITの常識力を身につけるために!
次期・ITソリューション塾・第48期(2025年2月12日 開講)
次期・ITソリューション塾・第48期(2025年2月12日[水]開講)の募集を始めました。
次のような皆さんには、きっとお役に立つはずです。
- SI事業者/ITベンダー企業にお勤めの皆さん
- ユーザー企業でIT活用やデジタル戦略に関わる皆さん
- デジタルを武器に事業の改革や新規開発に取り組もうとされている皆さん
- IT業界以外から、SI事業者/ITベンダー企業に転職された皆さん
- デジタル人材/DX人材の育成に関わられる皆さん
ITに関わる仕事をしている人たちは、いま起こりつつある変化の背景にあるテクノロジーを正しく理解し、自分たちのビジネスに、あるいは、お客様への提案に、活かす方法を見つけなくてはなりません。
ITソリューション塾は、そんなITの最新トレンドを体系的に分かりやすくお伝えするとともに、ビジネスとの関係やこれからの戦略を解説し、どのように実践につなげればいいのかを考えます。
詳しくはこちらをご覧下さい。
※神社の杜のワーキング・プレイス 8MATO(やまと)会員の皆さんは、参加費が無料となります。申し込みに際しましては、その旨、通信欄にご記入ください。
- 期間:2025年2月12日(水)〜最終回4月23日(水) 全10回+特別補講
- 時間:毎週(水曜日*原則*) 18:30〜20:30 の2時間
- 方法:オンライン(Zoom)
- 費用:90,000円(税込み 99,000円)
- 内容:
- デジタルがもたらす社会の変化とDXの本質
- IT利用のあり方を変えるクラウド・コンピューティング
- これからのビジネス基盤となるIoTと5G
- 人間との新たな役割分担を模索するAI
- おさえておきたい注目のテクノロジー
- 変化に俊敏に対処するための開発と運用
- アジャイルの実践とアジャイルワーク
- クラウド/DevOps戦略の実践
- 経営のためのセキュリティの基礎と本質
- 総括・これからのITビジネス戦略
- 特別補講 :選考中
6月22日・販売開始!【図解】これ1枚でわかる最新ITトレンド・改訂第5版
生成AIを使えば、業務の効率爆上がり?
このソフトウェアを導入すれば、DXができる?
・・・そんな都合のいい「魔法の杖」はありません。
神社の杜のワーキング・プレイス 8MATO
8MATOのご紹介は、こちらをご覧下さい。