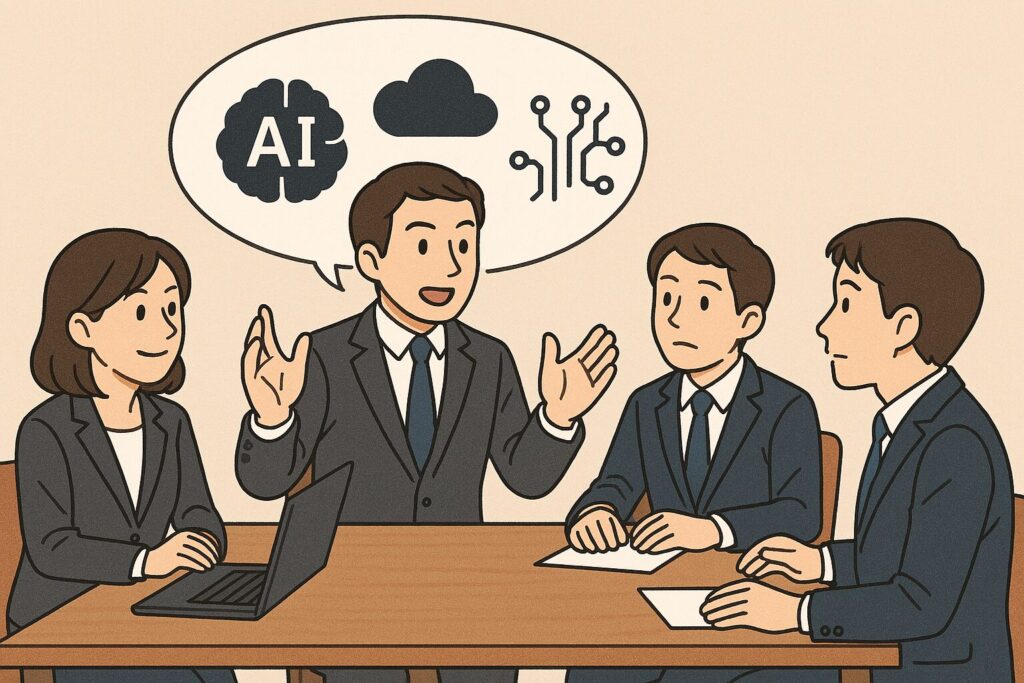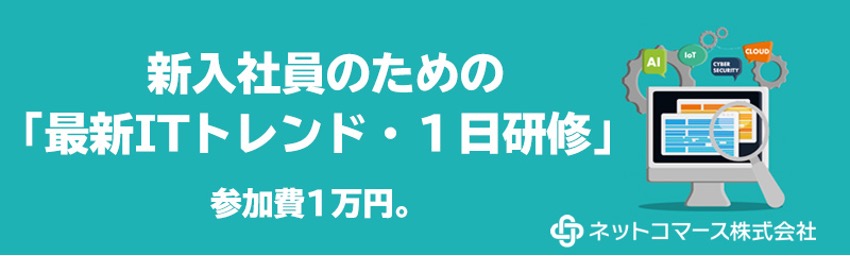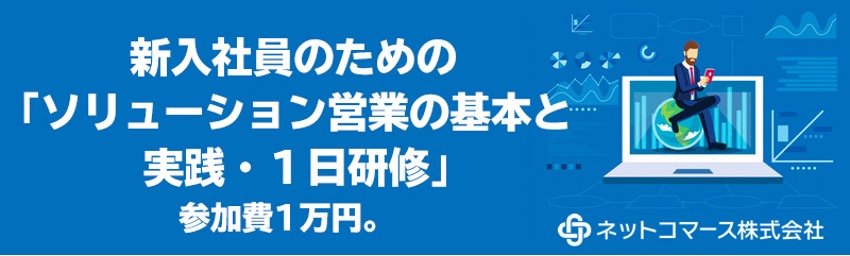「AIが営業の仕事を奪う」
このフレーズを耳にすることがよくあります。確かに、製品情報や課題解決の方法などを調べるには、いちいち営業に尋ねるよりも、ChatGPTのようなAIツールを使って方が手間はありません。しかし、営業の役割はそれだけではありません。AIの性能や機能が急速に向上するいま、あらためて「営業の基本」が、これまで以上に問われていると感じています。
古い営業スタイルが終わる日
これまでのSI/IT業界の営業は「何を売るか」を軸に動いてきました。
「この製品なら御社の課題を解決できます」
「御社の要望に沿ったシステム開発ならお任せ下さい」
「工数はこれくらいかかりますので、予算はこちらでいかがでしょうか」
こうした「モノや工数を売る」営業スタイルが長年、業界の標準でした。これは、世界がより予測可能で、お客様が「解決すべき課題」を明確に定義できた時代には有効でした。
しかし今や状況は根本から変わっています。変化の速度は加速し、不確実性は日々高まっています。昨日の「正解」が今日も「正解」である保証はなく、明日はさらに変わるかもしれません。DX、AI、サステナビリティ、高齢化社会、働き方改革などが同時に押し寄せる中で、多くのお客様は「自分たちが本当に解決すべき課題は何か」さえも明確に定義できない状況に置かれています。
先日、ある製造業のCIOからこんな言葉を投げかけられました。
「正直に言うと、ITベンダーに頼んできた仕事の8割は、うちの若手社員がノーコードツールとAIで、自分たちで作れるようになりました。残りの2割も、クラウドサービスを組み合わせればほとんど対応できます。でも、それよりも困っているのは、この先10年、我々はどんな技術をどう活用すれば生き残れるのか、その道筋が見えないことなんです。残念ながら、ITベンダーにこんな相談をしても、まともな答えが返ってこないのは、本当に残念です。」
この言葉は、IT/SI営業への痛烈な警告であると同時に、新たな可能性を示すものでもあるでしょう。
新たな営業の姿/「提言営業」という教師の役割
AIが普及し不確実性が高まる世界で、営業はお客様に何を提供すべきなのでしょうか?
一つは「利他の精神に基づく、お客様の経営と事業への深い理解と共感」。二つ目は「ITの本質を理解する確かな基礎知識」。そして三つ目が「お客様自身も気づいていない課題を発見し、解決策を提言する教師としての姿勢」です。
この三つ目の視点は、特に重要だと考えています。今日の複雑な社会環境において、お客様が課題を明確に定義できず、「何が欲しいか」を具体的に言語化できないケースが増えているからです。そんな時、従来の「お客様の要望に応える」スタイルではお客様の求める価値を提供できません。
むしろ必要なのは、お客様より一歩先を行き、潜在的な課題とその解決策を積極的に提言し、これを起点に対話を始める「提言営業」のアプローチです。言わば、お客様の「先生」「教師」となって、新たな視点や知識を提供する役割です。
基礎を制する者が応用を制す
「でも、お客様の先生になるなんて、おこがましいのでは?」
先生というのは、「全てを知っている」ことではなく、基礎や基本をしっかりと心得ている人のことです。どうすればいいかを迷ったとき、新しい技術やサービスが登場したとき、どうすればいいかを基礎や本に立ち返り、原理原則に基づいて、物事を考え、答えを作れる能力を持った人材です。そして、その応えに基づいて、道を示すことができることです。
そんな先生となるためには、ITの基礎知識だけでなく、幅広い視野と深い洞察力が不可欠です。そんな知識を身につけるには、次のようなアプローチが役に立つかも知れません。
- 歴史を学ぶ:コンピュータの歴史、インターネットの発展史、プログラミング言語の進化など、「なぜそうなったのか」を理解することで、未来の方向性も見えてくる
- 基礎概念を押さえる:アルゴリズム、データ構造、ネットワーク理論、データベース設計の基本原理など、技術の「なぜ」を理解する
- 現場の声を聞く:自社のエンジニアから実装の苦労話を聞いたり、開発会議に参加したりして、技術の現実的な制約や可能性を理解する
- 越境学習をする:IT以外の分野(経営学、心理学、デザイン思考、サステナビリティ、社会学など)も学ぶことで、技術と社会をつなぐ視点を養う
- 学んだことを言語化する習慣:新しく学んだ概念を、技術に詳しくない人にも分かるように説明する練習をする
- 社会課題と技術の接点を考える:高齢化、環境問題、格差など、社会課題に技術がどう貢献できるかを常に考える
さらに、以下のような習慣も身につける心がけが大切です。
- お客様の業界の10年先を想像する:現在のトレンドから、お客様の業界がどう変化していくかを予測し、仮説を立てる
- 「もし私が経営者なら」という思考実験:お客様の立場に立ち、経営者として何を決断すべきかを考える
- 異業種からの学び:全く異なる業界での成功事例を研究し、お客様の業界に応用できないか考える
お客様の先生になるとは、すべてを知っているということではなく、お客様と一緒に考えながら、自らが持つ基礎や基本、原理や原則に照らして、未来への道筋を示す役割を果たすことです。
不確実性の時代に「売らずして売れる」関係を築く
「でも、結局は売上目標があるじゃないか」
確かにその通りです。ただ、不思議なことに、「相手の幸せを第一に考える」という利他の精神と「本質を理解した確かな知識」を兼ね備え、さらに「お客様の先生」として課題と解決策を提言できると、長期的には営業数字も自然と伸びていくのです。
例えば、当初はシステム保守の小さな案件だけでしたが、お客様の事業について勉強し、時には「このままでは5年後に陳腐化するリスクがあります」と厳しい意見も率直に伝え、共に考える姿勢を続け、最新のAI技術について「なぜそれが可能になったのか」を技術的背景から説明し、さらには「御社が取り組むべき次の課題は○○です」と具体的な提言を行っていたとしましょう。
すぐには数字にはならないかも知れませんが、お客様はあなたの誠実さと、しっかりとした知識に支えられた話しに、少し耳を傾けるようになるはずです。
「新しいプロジェクトを始めることになった。他社にも声をかけるつもりだったが、やっぱり君たちにお願いしたい。来週から一緒に企画を詰めてくれないか」
突然こんな話しが舞い込んで来てもおかしくはありません。お客様の知らない課題を指摘し、その解決策を示し続けることで、信頼の土台は築かれていきます。そうなることが、先生であり教師になるということです。そんな関係を築くことができれば、売り込む必要はありません。
AIと共に歩む教師型営業の実践
こうした「提言営業」への変革を実現するには、私たち自身がAIを積極的に活用する必要があります。
例えば:つぎのようなことです。
- お客様の業界の将来シナリオを複数描くために、AIを使って未来を予測する
- 社会課題(SDGs、高齢化対応、レジリエンス強化など)とITの接点を探るために、AIで多様な事例を収集・分析する
- 提言の説得力を高めるために、AIで視覚化資料や具体的なプロトタイプを短時間で作成する
お客様に何をして欲しいのかを尋ねそれに応えることしかできないとすれば、「AIに仕事を奪われる」ことは覚悟しなくてはなりません。「AIと共に学び、お客様の教師となる」ことを目指せば、お客様からの信頼を積み重ねていくことができます。
明日から始める「教師型営業」への一歩
では、具体的にどのように「提言営業」へのシフトを始めればよいのでしょうか。
- お客様への問いかけを変える:「何かお困りごとはありますか?」ではなく、「○○業界は今後3年でこう変わると予測されていますが、御社はどうお考えですか?」と問いかける
- 勉強会を主催する:お客様を招いて「AI活用の最前線」などのテーマで小規模勉強会を開き、教える側の経験を積む
- ブログやニュースレターで発信する:業界動向や技術トレンドについての独自の見解を発信し、「教える」練習をする
- 提言書の作成習慣をつける:毎月1つ、担当するお客様に向けた「こうすべき」提言書を作成する(提出しなくても良い)
- 「教えるための15分」を作る:商談の中に、「最新技術動向をお伝えする15分」などの枠を意図的に作り、教える習慣をつける
ここにしめしたことを考えてからやるかどうかの結論を出すのではなく、まずは行動に移して下さい。やってみてどうすればいいかを考えて下さい。もしうまくいかなければ、もっと他の良いやり方を考えてはいかがでしょう。考えてから行動するのではなく、行動してから考えた方が、確実に、そして短期間にスキルを磨くことができます。なによりも、将来の予測が難しいで時代ですから、絶対の正解など見つけることは難しく、行動して、感じて、考えて、再び行動するというのが、現実に即しています。
不確実性の時代の羅針盤
不確実な時代だからこそ、確かな基礎と揺るがぬ利他の精神を持つことです。お客様の利益を第一に考えれば、自分の利益は後からついてきます。お客様の幸せを願えない営業には、その人の幸せも訪れません。そして、本当にお客様を助けたいなら、表面的な知識ではなく、本質を理解し、時に先生となって道を照らす行動をとるべきです。
AIがどれだけ進化しても、「相手の幸せを願う心」と「本質を理解する知識」、そして「未来を照らす提言力」は決して代替されません。それはテクノロジーではなく、人間の「本性(ほんしょう)」に根ざす行動だからです。
SI/IT営業は今、大きな岐路に立っています。単なる「モノ売り」から脱却し、お客様の事業と経営を深く理解し、心から相手の幸せを願い、確かな基礎知識に裏打ちされた提案ができる「教師」へと進化できるかどうかが、AI時代を生き抜く鍵となります。
今年も開催!新入社員のための1日研修・1万円
AI前提の社会となり、DXは再定義を余儀なくされています。アジャイル開発やクラウドネイティブなどのモダンITはもはや前提です。しかし、AIが何かも知らず、DXとデジタル化を区別できず、なぜモダンITなのかがわからないままに、現場に放り出されてしまえば、お客様からの信頼は得られず、自信を無くしてしまいます。
営業のスタイルも、求められるスキルも変わります。AIを武器にできれば、経験が浅くてもお客様に刺さる提案もできるようになります。
本研修では、そんないまのITの常識を踏まえつつ、これからのITプロフェッショナルとしての働き方を学び、これから関わる自分の仕事に自信とやり甲斐を持ってもらおうことを目的としています。
参加費:
- 1万円(税込)/今年社会人となった新入社員と社会人2年目
- 2万円(税込)/上記以外
お客様の話していることが分かる、社内の議論についてゆける、仕事が楽しくなる。そんな自信を手にして下さい。
現場に出て困らないための最新トレンドをわかりやすく解説。 ITに関わる仕事の意義や楽しさ、自分のスキルを磨くためにはどうすればいいのかも考えます。詳しくはこちらをご覧下さい。
100名/回(オンライン/Zoom)
いずれも同じ内容です。
【第1回】 2025年6月10日(火)
【第2回】 2025年7月10日(木)
【第3回】 2025年8月20日(水)
営業とは何か、ソリューション営業とは何か、どのように実践すればいいのか。そんな、ソリューション営業活動の基本と実践のプロセスをわかりやすく解説。また、現場で困難にぶつかったり、迷ったりしたら立ち返ることができるポイントを、チェック・シートで確認しながら、学びます。詳しくはこちらをご覧下さい。
100名/回(オンライン/Zoom)
2025年8月27日(水)
【図解】これ1枚でわかる最新ITトレンド・改訂第5版
生成AIを使えば、業務の効率爆上がり?
このソフトウェアを導入すれば、DXができる?
・・・そんな都合のいい「魔法の杖」はありません。
神社の杜のワーキング・プレイス 8MATO
8MATOのご紹介は、こちらをご覧下さい。